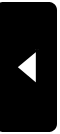2015年09月10日
砲塔の組み立て(2)
タミヤ新金型のティーガーⅠ初期型、素組みの最終段階です。
砲塔を組んで、最後にスカートを細工します。

部品は注意して見ないと、思わぬところにバリがあります。
スカートの細工は今回、初めての方法ですが、
セパレートにしてしまおうと考えています。

ゲペックカステンは珍しく、底蓋を接着するようになっています。
普通は上蓋なんですけどね。

砲身の接合面の線消しは、ちょっとまだ甘いかなと。
基本塗装の段階で見直しましょう。

予備履帯は私の選択したタイプでは取り付けないようになっています。
寂しいですねぇ。
何か着けたいですねぇ・・・・。

スカートのパーツごとのズレを出すために片側4枚を切り離しました。
これだけでも全然効果が違いますね。

まずまずいい感じで素組みを完了しました。
砲塔を組んで、最後にスカートを細工します。
部品は注意して見ないと、思わぬところにバリがあります。
スカートの細工は今回、初めての方法ですが、
セパレートにしてしまおうと考えています。
ゲペックカステンは珍しく、底蓋を接着するようになっています。
普通は上蓋なんですけどね。
砲身の接合面の線消しは、ちょっとまだ甘いかなと。
基本塗装の段階で見直しましょう。
予備履帯は私の選択したタイプでは取り付けないようになっています。
寂しいですねぇ。
何か着けたいですねぇ・・・・。
スカートのパーツごとのズレを出すために片側4枚を切り離しました。
これだけでも全然効果が違いますね。
まずまずいい感じで素組みを完了しました。
2015年09月09日
ツェメリットコーティング
タミヤのティーガーⅠ中期型です。
さっそくツェメリットを始めています。
老眼との闘いですね。

ポリエステルパテと硬化剤をこれくらいの割合で混ぜます。
硬化剤が少なくても、多すぎても、硬化に障害が起きますね。
また臭気が強いので、換気は欠かせません。

側面から始めました。別に理由はないのですが・・・・。
相変わらずムラが出ます。
ブレードの着圧をうまくコントロール出来ません。
老眼の進行も辛いです。

スカートの線を切り出しました。
すき間が出来たら、パステル粉でのウェザリングで隠せます。

ツェメリットのはげ落ちを作りました。
カッターナイフを引っ掛けてしまったところを隠すためです。
まあ、このくらいはよくあることで・・・・。

リアパネルにもコーティング出来ました。
細かいところは後で修正したり、一番汚れる部分ですから、
ごまかしの方法はいくつもあります。
そういう技術も時には役立ちます。
初期型が残っていたので、素組みを完了させましょう。
さっそくツェメリットを始めています。
老眼との闘いですね。
ポリエステルパテと硬化剤をこれくらいの割合で混ぜます。
硬化剤が少なくても、多すぎても、硬化に障害が起きますね。
また臭気が強いので、換気は欠かせません。
側面から始めました。別に理由はないのですが・・・・。
相変わらずムラが出ます。
ブレードの着圧をうまくコントロール出来ません。
老眼の進行も辛いです。
スカートの線を切り出しました。
すき間が出来たら、パステル粉でのウェザリングで隠せます。
ツェメリットのはげ落ちを作りました。
カッターナイフを引っ掛けてしまったところを隠すためです。
まあ、このくらいはよくあることで・・・・。
リアパネルにもコーティング出来ました。
細かいところは後で修正したり、一番汚れる部分ですから、
ごまかしの方法はいくつもあります。
そういう技術も時には役立ちます。
初期型が残っていたので、素組みを完了させましょう。
2015年09月08日
製作開始!!
タミヤのティーガーⅠ中期型の製作を開始します。
イメージはノルマンディの3色迷彩、ツェメリットという、
いわば総花的な感じですね。
組立図に沿ってリアパネルから行きます。

足回りはここではトーションバーまでです。
ホイールは塗装後に取り付けます。
履帯は極初期や初期型と違って連結式になっています。

ツェメリットのためのガイド線がつけられています。
メーカーの心遣いが読み取れます。
リアパネルには取り付ける部品も多いので、
取り付け前にガイド線に沿ってコーティングが出来れば
本当に助かるんですね。

側面装甲板にも、スカートの取り付け線が示されています。
スカートはダメージ表現の宝庫みたいなもので、
ティーガーⅠの場合は片側4枚連結式ですが、
これを部分的に脱落させたり、ひん曲げたりしてダメージを
醸し出すわけです。
こういうガイド線があれば、脱落させる時も、
どこまでコーティングすればよいかが判明して、
大変やり易いですね。

今日はここまでです。
いよいよツェメリットを始めて行きます。
(つづく)
イメージはノルマンディの3色迷彩、ツェメリットという、
いわば総花的な感じですね。
組立図に沿ってリアパネルから行きます。
足回りはここではトーションバーまでです。
ホイールは塗装後に取り付けます。
履帯は極初期や初期型と違って連結式になっています。
ツェメリットのためのガイド線がつけられています。
メーカーの心遣いが読み取れます。
リアパネルには取り付ける部品も多いので、
取り付け前にガイド線に沿ってコーティングが出来れば
本当に助かるんですね。
側面装甲板にも、スカートの取り付け線が示されています。
スカートはダメージ表現の宝庫みたいなもので、
ティーガーⅠの場合は片側4枚連結式ですが、
これを部分的に脱落させたり、ひん曲げたりしてダメージを
醸し出すわけです。
こういうガイド線があれば、脱落させる時も、
どこまでコーティングすればよいかが判明して、
大変やり易いですね。
今日はここまでです。
いよいよツェメリットを始めて行きます。
(つづく)
2015年09月07日
車体上部の組み立て(3)
タミヤのヴィルベルを続けています。
OVMそのものは他のⅣ号ファミリーの戦車と同じですが、
取り付け位置はかなりイレギュラーな感じですね。
こういう時は他のOVM、アクセサリーパーツを
思い切って増やすのがいいです。

この辺はいつものポイントってとこですね。

予備転輪はここに来ます。
今回は予備履帯を多く使ってみようと考えています。

機銃は例によって銃口を開けています。
100均の超極細ピンバイスが有効に働いています。

スパナはエッチングパーツですが、少しサイズが大きいようです。

前にも書いたように、今回はボッシュライトを選択したのですが、
フェンダーの穴はノテック用のもので、ボッシュ用の穴はありません。
新たに開けて接着します。

ノテック用の穴はあとで埋めなければなりません。
ここまでまずまず順調なヴィルベルです。
OVMそのものは他のⅣ号ファミリーの戦車と同じですが、
取り付け位置はかなりイレギュラーな感じですね。
こういう時は他のOVM、アクセサリーパーツを
思い切って増やすのがいいです。
この辺はいつものポイントってとこですね。
予備転輪はここに来ます。
今回は予備履帯を多く使ってみようと考えています。
機銃は例によって銃口を開けています。
100均の超極細ピンバイスが有効に働いています。
スパナはエッチングパーツですが、少しサイズが大きいようです。
前にも書いたように、今回はボッシュライトを選択したのですが、
フェンダーの穴はノテック用のもので、ボッシュ用の穴はありません。
新たに開けて接着します。
ノテック用の穴はあとで埋めなければなりません。
ここまでまずまず順調なヴィルベルです。
2015年09月06日
車体上部の組み立て(2)
タミヤ新金型のⅣ号対空戦車ヴィルベルヴィントです。
車体上部の組み立てを続けます。
Ⅳ号ファミリーの戦車ですが、あまり見慣れない部品もあります。

予備銃身のケースですって。
4連装機銃の予備の銃身を入れておく訳ですね。
こういうのはダメージ表現がし難いんですよね。

予備転輪を組みましたが、外輪ゴムの真ん中にあった
いつものパー線がありません。
ほんの少しだけ出ているだけです。
他の転輪部品もそのようなので、これは助かります。

ジャッキは3つの部品からできています。
ダークアイアンで光らせてから、鉄錆びを入れていきます。

このハッチは枠に対してサイズが小さいので、
接着するとき慎重に真ん中に置かないと、
隙間がアンバランスになってしまいます。
スミ入れもやり難くなりますから要注意です。
(つづく)
車体上部の組み立てを続けます。
Ⅳ号ファミリーの戦車ですが、あまり見慣れない部品もあります。
予備銃身のケースですって。
4連装機銃の予備の銃身を入れておく訳ですね。
こういうのはダメージ表現がし難いんですよね。
予備転輪を組みましたが、外輪ゴムの真ん中にあった
いつものパー線がありません。
ほんの少しだけ出ているだけです。
他の転輪部品もそのようなので、これは助かります。
ジャッキは3つの部品からできています。
ダークアイアンで光らせてから、鉄錆びを入れていきます。
このハッチは枠に対してサイズが小さいので、
接着するとき慎重に真ん中に置かないと、
隙間がアンバランスになってしまいます。
スミ入れもやり難くなりますから要注意です。
(つづく)
2015年09月05日
車体上部の組み立て(1)
タミヤ新金型のⅣ号対空戦車ヴィルベルヴィントです。
車体上部を組み立てて行きます。
新金型の部品ですが、割とパー線が多いですかねぇ。

エッチングパーツはまだ使えるものが残っています。

8番、9番と12番ですね。
瞬接で取り付けます。

パー線が多いことを除けば、部品の質は悪くありません。
ていねいに組んで行きたいですね。

前照灯はボッシュライトかノテックライトを選択するのですが、
組立図に何も書いていないので、両方とも組んでしまいそうになります。
ここではボッシュライトを選択しました。
(つづく)
車体上部を組み立てて行きます。
新金型の部品ですが、割とパー線が多いですかねぇ。
エッチングパーツはまだ使えるものが残っています。
8番、9番と12番ですね。
瞬接で取り付けます。
パー線が多いことを除けば、部品の質は悪くありません。
ていねいに組んで行きたいですね。
前照灯はボッシュライトかノテックライトを選択するのですが、
組立図に何も書いていないので、両方とも組んでしまいそうになります。
ここではボッシュライトを選択しました。
(つづく)
2015年09月04日
車体上部の仕上げ(7)
タミヤのⅣ突、パステル粉やってます。
戦闘室天面の防弾版で局部的にやってみます。
教本のイメージを大事にして進めます。

明るめの茶を置いたあとに、別の濃いめの茶を粉の状態で置きます。
置き易いようにキットの角度を変えています。
かためてボンと置くのではなく、あくまでもムラに置きます。

これで角度を戻すと、大半の粉が落ちますが、
残った粉はいい感じを出してくれます。
そこへアクリル溶剤を浸透させて固定します。

オレンジでアクセントをつけます。

溶剤を染み込ませるとオレンジはほとんど消えます。
そこへ今度は黒を置きます。
同様に溶剤を染み込ませます。

続いてグレーを置き、最後にもう一度濃いめの茶を置きます。
これでいい感じに仕上がりました。
最後に違和感をなくすため、小さな周囲の鉄錆びを調整します。

なかなかいい感じに出来ました。
もちろん自己満足です。
あともう一回上部の調整をやって、いよいよ車体下部に進みます。
戦闘室天面の防弾版で局部的にやってみます。
教本のイメージを大事にして進めます。
明るめの茶を置いたあとに、別の濃いめの茶を粉の状態で置きます。
置き易いようにキットの角度を変えています。
かためてボンと置くのではなく、あくまでもムラに置きます。
これで角度を戻すと、大半の粉が落ちますが、
残った粉はいい感じを出してくれます。
そこへアクリル溶剤を浸透させて固定します。
オレンジでアクセントをつけます。
溶剤を染み込ませるとオレンジはほとんど消えます。
そこへ今度は黒を置きます。
同様に溶剤を染み込ませます。
続いてグレーを置き、最後にもう一度濃いめの茶を置きます。
これでいい感じに仕上がりました。
最後に違和感をなくすため、小さな周囲の鉄錆びを調整します。
なかなかいい感じに出来ました。
もちろん自己満足です。
あともう一回上部の調整をやって、いよいよ車体下部に進みます。
2015年09月03日
車体上部の仕上げ(6)
タミヤ旧金型のⅣ号突撃砲です。
車体上部の仕上げを進めて来ました。
鉄錆び表現を局部的にやってみましょう。

これは教本に示されている写真です。
ケーニッヒスの凄いリアルな鉄錆びです。
特にスカートの部分・・・・。

ここまで多くの鉄錆びを描いて来ましたが、
常にイメージとしてあったのはこの部分です。
全く違和感のない、見事な仕上がりと思います。
で、パステル粉を用いてやってみましょう。

この砲塔天面の防弾版内側ですが、
くっきりとしたピン痕がありましたので、
これを隠ぺいするのを兼ねて固定錆びを描いて行きます。
エナメルのこげ茶でまずは下書きをします。

アクリル溶剤で明るめの茶色を微量取り、
下書きの上から置いて行きます。
下書き部分を残すように置くのがいいでしょう。
ここからがパステル粉の面白いところになって来ます。
(つづく)
車体上部の仕上げを進めて来ました。
鉄錆び表現を局部的にやってみましょう。
これは教本に示されている写真です。
ケーニッヒスの凄いリアルな鉄錆びです。
特にスカートの部分・・・・。
ここまで多くの鉄錆びを描いて来ましたが、
常にイメージとしてあったのはこの部分です。
全く違和感のない、見事な仕上がりと思います。
で、パステル粉を用いてやってみましょう。
この砲塔天面の防弾版内側ですが、
くっきりとしたピン痕がありましたので、
これを隠ぺいするのを兼ねて固定錆びを描いて行きます。
エナメルのこげ茶でまずは下書きをします。
アクリル溶剤で明るめの茶色を微量取り、
下書きの上から置いて行きます。
下書き部分を残すように置くのがいいでしょう。
ここからがパステル粉の面白いところになって来ます。
(つづく)
2015年09月02日
やっぱり2号!!
むかしNHKで放映されていたサンダーバードが、今また、やってますね。
凄い、懐かしいというか、私のプラモデル道に大きな影響を与えた番組でしたから。

今井科学からキットが発売されていて、
1号から5号まで全部作りました。
3号が小さかった(5号のキットに付属)のですが、
実際はロケットの中では3号が一番大きかったんですね。

でもやっぱり一番好きだったのは2号ですね。
輸送機として、いくつもの装備を運んでいました。
4号もその一つでしたね。
今年復活したサンダーバードですが、
旧バージョンと比べて・・・・、どうですかね?
私は今一かと思うのですがね。
CGでフィギュアの動きは段違い。
ロケットや各種装備の動きも軽快というか、
まあ、はっきり言ってアニメの世界ですね。

2号の天井ハッチを手動で開閉するなど、
ウソのような新バージョンですしね・・・・。
旧バージョンから飛躍し過ぎというのが私の印象です。
でもTVはもれなく見ています。
凄い、懐かしいというか、私のプラモデル道に大きな影響を与えた番組でしたから。

今井科学からキットが発売されていて、
1号から5号まで全部作りました。
3号が小さかった(5号のキットに付属)のですが、
実際はロケットの中では3号が一番大きかったんですね。

でもやっぱり一番好きだったのは2号ですね。
輸送機として、いくつもの装備を運んでいました。
4号もその一つでしたね。
今年復活したサンダーバードですが、
旧バージョンと比べて・・・・、どうですかね?
私は今一かと思うのですがね。
CGでフィギュアの動きは段違い。
ロケットや各種装備の動きも軽快というか、
まあ、はっきり言ってアニメの世界ですね。

2号の天井ハッチを手動で開閉するなど、
ウソのような新バージョンですしね・・・・。
旧バージョンから飛躍し過ぎというのが私の印象です。
でもTVはもれなく見ています。
2015年09月01日
私の技法(再)
どこで手に入れた情報でしたか・・・・?
ユザワヤさんで売っていると、千葉にいた時、購入しました。

茶こしで削って粉状にします。
とっても細かい粉末になります。
1/35の模型ですから、すべてが1/35になるわけで、
粉末も細かいに限ります。
じゃ、色はどんなにあるの?

今、私の手元にあるのはこれだけです。
たいてい、間に合います。

パステルには、このような印字があります。
「ヌーベル・カレー・パステル」と読むそうです。
有名なのかな?
とにかく、一本70円ほどで、うまく利用できています。
タミヤのウェザリングマスターよりも割安です。
おすすめの逸品です。
ユザワヤさんで売っていると、千葉にいた時、購入しました。

茶こしで削って粉状にします。
とっても細かい粉末になります。
1/35の模型ですから、すべてが1/35になるわけで、
粉末も細かいに限ります。
じゃ、色はどんなにあるの?

今、私の手元にあるのはこれだけです。
たいてい、間に合います。

パステルには、このような印字があります。
「ヌーベル・カレー・パステル」と読むそうです。
有名なのかな?
とにかく、一本70円ほどで、うまく利用できています。
タミヤのウェザリングマスターよりも割安です。
おすすめの逸品です。