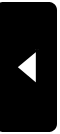2014年07月11日
素組み完了
ドラゴンのナースホルン、素組みの最終段階です。
ただ、戦闘室内部の塗装を考え、装甲板は前面だけ開けておきます。
最後の部品群です。

惑わされ、困らされ、ここまで辿り着いた感じです。
あとこれだけ組んだら一段落かと思うと、
感慨深いものがありますね。
主砲のトラベリングロックですが、
これも主砲の塗装が終わってから固定するため、
ここでは接着はしません。

ナースホルンの素組みを終わります。
在庫の中にフンメルがありますが、
着手までちょっと長めの間を置こうと思います。
ただ、戦闘室内部の塗装を考え、装甲板は前面だけ開けておきます。
最後の部品群です。
惑わされ、困らされ、ここまで辿り着いた感じです。
あとこれだけ組んだら一段落かと思うと、
感慨深いものがありますね。
主砲のトラベリングロックですが、
これも主砲の塗装が終わってから固定するため、
ここでは接着はしません。
ナースホルンの素組みを終わります。
在庫の中にフンメルがありますが、
着手までちょっと長めの間を置こうと思います。
2014年07月10日
戦闘室の組立て
ドラゴンのナースホルンです。
戦闘室を組みます。

まず、馬の耳のようなパネルを組みます。
ちなみにここでも部品番号の誤表記がありました。
次にこれは、トラベリングロックの解除ハンドルですかね。
ロッキング状態で組むので、ハンドルは寝かさず起こしています。

次は苦心して作った砲弾ラックです。
でも組立図には取り付け位置の明確な指示がありません。
先の耳状部品にくっつけろとのことなので、
怖いですが、その通りにします。

砲弾ラックのうしろから、防弾板を取り付けます。

左右揃えて戦闘室が組み上がります。

前回作った後部ゲートも取り付けてOKです。

いつもはこの辺で合わないとか、ずれてるとかトラブるのですが、
今回はスムースです。
戦闘室を組みます。
まず、馬の耳のようなパネルを組みます。
ちなみにここでも部品番号の誤表記がありました。
次にこれは、トラベリングロックの解除ハンドルですかね。
ロッキング状態で組むので、ハンドルは寝かさず起こしています。
次は苦心して作った砲弾ラックです。
でも組立図には取り付け位置の明確な指示がありません。
先の耳状部品にくっつけろとのことなので、
怖いですが、その通りにします。
砲弾ラックのうしろから、防弾板を取り付けます。
左右揃えて戦闘室が組み上がります。
前回作った後部ゲートも取り付けてOKです。
いつもはこの辺で合わないとか、ずれてるとかトラブるのですが、
今回はスムースです。
2014年07月09日
リア・ゲートの組立て
ドラゴンのナースホルンを続けます。
後部戦闘室の入口を組みます。
ここは開状態にして組みます。

エッチングパーツもあり、ていねいに、
そして組立図に騙されないように進めます。

エッチング挟みが使用出来ない時はナイフで切り取ります。

切り取り痕をダイヤモンドやすりで削ります。

ヤットコで折り曲げます。
力が入り過ぎないように注意します。


無事に出来ました。
戦闘室がもうすぐ組み上がりますね。
後部戦闘室の入口を組みます。
ここは開状態にして組みます。
エッチングパーツもあり、ていねいに、
そして組立図に騙されないように進めます。
エッチング挟みが使用出来ない時はナイフで切り取ります。
切り取り痕をダイヤモンドやすりで削ります。
ヤットコで折り曲げます。
力が入り過ぎないように注意します。
無事に出来ました。
戦闘室がもうすぐ組み上がりますね。
2014年07月08日
誤表記にめげず
tドラゴンのナースホルンを続けます。
誤表記に遭うたびに気持ちがめげそうになるのですが・・・・。
砲弾ラックの部品を揃えます。

キットのイメージとして、情景は砲架もロックして、オープントップの戦闘室
では兵士たちが束の間の休息を味わっているというところを想定、
従って、砲弾ラックは左右2個あるので、オープンとクローズを1個ずつ
ということにしましょう。
クローズはすぐに出来ました。

実はクローズの中にも、砲弾をキッチリ組みこむように指示されています。
何か、意味があるのでしょうかね?
オープンの方は、前回にもあったように奥と手前で形状がことなりますが、
手前側は取り付け部品も合わせて精密に組み立てる指示になっています。
今回は片側の砲弾部品が余るので、オープンの砲弾をすべて奥側の砲弾
にして、ちょっと楽をしました。
出来上がると別に違和感ないですよね。

素組み完了まであと少しなので、
ナースホルンを続けます。
誤表記に遭うたびに気持ちがめげそうになるのですが・・・・。
砲弾ラックの部品を揃えます。
キットのイメージとして、情景は砲架もロックして、オープントップの戦闘室
では兵士たちが束の間の休息を味わっているというところを想定、
従って、砲弾ラックは左右2個あるので、オープンとクローズを1個ずつ
ということにしましょう。
クローズはすぐに出来ました。
実はクローズの中にも、砲弾をキッチリ組みこむように指示されています。
何か、意味があるのでしょうかね?
オープンの方は、前回にもあったように奥と手前で形状がことなりますが、
手前側は取り付け部品も合わせて精密に組み立てる指示になっています。
今回は片側の砲弾部品が余るので、オープンの砲弾をすべて奥側の砲弾
にして、ちょっと楽をしました。
出来上がると別に違和感ないですよね。
素組み完了まであと少しなので、
ナースホルンを続けます。
2014年07月07日
砲弾ラック
ドラゴンのナースホルンです。
暑い中、製作復活です。
砲弾のラックということですが、88㎜砲の砲弾といえば、
ティーガーⅠ用と、ケーニッヒス・ティーガー用の真鍮製がありまして、

ドラゴンの部品と比べましたが、どちらも不一致でした。残念!!
ということで、組立図に注意しながら進めます。
ラックには8本の砲弾を組みこみます。
奥に入る砲弾と手前のものでは、形状が異なります。
でも良く見ると・・・・。

組立図では奥が部品F20、手前がF4となっていますが、
実際の部品は・・・・。


真逆になっています。
またもや誤表記ですね。
これでいくつ目ですか?
ものすごい台風が近付いています。
暑い中、製作復活です。
砲弾のラックということですが、88㎜砲の砲弾といえば、
ティーガーⅠ用と、ケーニッヒス・ティーガー用の真鍮製がありまして、
ドラゴンの部品と比べましたが、どちらも不一致でした。残念!!
ということで、組立図に注意しながら進めます。
ラックには8本の砲弾を組みこみます。
奥に入る砲弾と手前のものでは、形状が異なります。
でも良く見ると・・・・。
組立図では奥が部品F20、手前がF4となっていますが、
実際の部品は・・・・。
真逆になっています。
またもや誤表記ですね。
これでいくつ目ですか?
ものすごい台風が近付いています。
2014年07月06日
2014年07月05日
2014年07月04日
主砲部の完成
88㎜砲の主砲部を完成させましょう。
昨日の続きで、オートマチックランマーの焼き止めの部分ですが、
新しい指示書があり、別部品を用いて焼き止めはしなくて済みそうです。

やっぱり火を使う危険を回避しようということですかね。
キャップ部品にてバーを可動状態で取り付けました。

ここまでで、主砲部の出来上がりです。



88㎜砲の射撃場面の映像を見ることが出来ました。
凄まじい威力が窺えますね。
昨日の続きで、オートマチックランマーの焼き止めの部分ですが、
新しい指示書があり、別部品を用いて焼き止めはしなくて済みそうです。
やっぱり火を使う危険を回避しようということですかね。
キャップ部品にてバーを可動状態で取り付けました。
ここまでで、主砲部の出来上がりです。
88㎜砲の射撃場面の映像を見ることが出来ました。
凄まじい威力が窺えますね。
2014年07月03日
砲架の組立て
88㎜砲を続けます。
砲架の組立てに進みます。
揺架、駐退復座機、オートマチックランマーと組んで行きます。

バリを細かく取って、部品の不備(ズレや反り、ピン痕、パー線等)をカバーします。
駐退復座機に至ってはキッチリ接着しても大きなズレがあり、
結果、明確なパーティングラインとなってしまいます。

やすりやデザインナイフで出っ張りを削り取り、線を消します。

オートマチックランマーでは、またまた焼き止めの指示がありました。
しかし、確かこの部分は新しい指示書があったはずで・・・・。
もうすぐ切りのいいところなので、88㎜砲をもう少し続けます。
砲架の組立てに進みます。
揺架、駐退復座機、オートマチックランマーと組んで行きます。
バリを細かく取って、部品の不備(ズレや反り、ピン痕、パー線等)をカバーします。
駐退復座機に至ってはキッチリ接着しても大きなズレがあり、
結果、明確なパーティングラインとなってしまいます。
やすりやデザインナイフで出っ張りを削り取り、線を消します。
オートマチックランマーでは、またまた焼き止めの指示がありました。
しかし、確かこの部分は新しい指示書があったはずで・・・・。
もうすぐ切りのいいところなので、88㎜砲をもう少し続けます。
2014年07月02日
側面版の組立て
タミヤ旧金型の88㎜砲Flak36です。
砲架の側面板を組みます。
部品はこれだけ。
以前に組んだ部品もあります。

バリが多く、パーティングラインもいっぱいです。
細かく除いていかないと、きっちり接合できなかったりして、
可動部分が可動しないとか、トラブルの原因になります。
このキットはプラスティックも柔らかいので、本当によく注意しないと
削り過ぎたりしてしまいます。

ほとんどトラブルなく組めました。
次は砲架に進みます。
今日はこれからゴミ出しです。
砲架の側面板を組みます。
部品はこれだけ。
以前に組んだ部品もあります。
バリが多く、パーティングラインもいっぱいです。
細かく除いていかないと、きっちり接合できなかったりして、
可動部分が可動しないとか、トラブルの原因になります。
このキットはプラスティックも柔らかいので、本当によく注意しないと
削り過ぎたりしてしまいます。
ほとんどトラブルなく組めました。
次は砲架に進みます。
今日はこれからゴミ出しです。
2014年07月01日
機銃座の取り付け
タミヤ旧金型のメーベルワーゲンです。
前回組んだ機銃座を台座に取り付けます。
台座、機銃座以外の部品は少ないのですが・・・・。

機銃座は角度が変動出来るようにしないといけませんので、
こんななつかしい指示がありました。

写真の赤丸の部分を『焼き止め』せよとのこと。
焼き止めなんて、もう何年もやっていません。
ドライバーもプラスはいっぱいあるのですが、
マイナスが見当たらず・・・・。
結局、はさみを使って焼き止めしました。
溶かした痕は指で丸めたり、やすりで整形します。
何とかうまく出来ました。


無事、動いてくれました。
感謝!! 感謝!!
前回組んだ機銃座を台座に取り付けます。
台座、機銃座以外の部品は少ないのですが・・・・。
機銃座は角度が変動出来るようにしないといけませんので、
こんななつかしい指示がありました。
写真の赤丸の部分を『焼き止め』せよとのこと。
焼き止めなんて、もう何年もやっていません。
ドライバーもプラスはいっぱいあるのですが、
マイナスが見当たらず・・・・。
結局、はさみを使って焼き止めしました。
溶かした痕は指で丸めたり、やすりで整形します。
何とかうまく出来ました。
無事、動いてくれました。
感謝!! 感謝!!